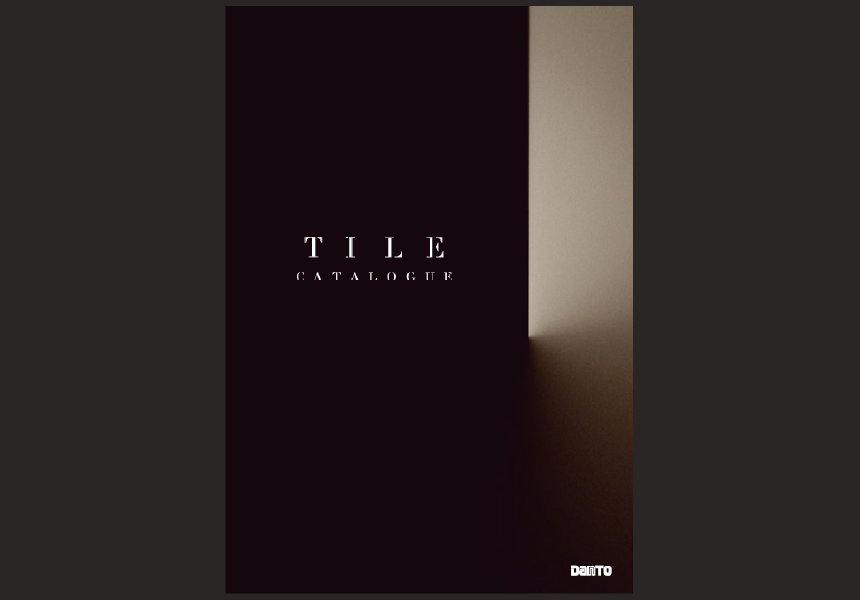こんにちは。淡陶社のタイル研究室です。
今回のタイル研究室では、「タイルのある暮らし」というテーマで、タイルという素材が空間や暮らしにどのような豊かさをもたらしてくれるのかについて、少し経済の視点も交えて掘り下げてみたいと思います。
私たちが日々取り扱っているタイルは、単なる仕上げ材ではありません。その一枚一枚に「空間をどう使いたいか」「どんな気持ちで過ごしたいか」といった、暮らしに対する想いが込められています。
今回はそんな視点から、タイルの価値を改めて見つめてみたいと思います。最後までご覧いただければ幸いです。
タイルのある暮らしとは
タイルが選ばれる暮らしには、共通して“丁寧さ”や“美意識”が漂っています。それは、目立ちすぎず、静かに空間に溶け込みながらも、確かな存在感を放つ素材です。
玄関の一角、キッチンの壁、洗面台のまわり。ほんの少しの面積でも、タイルがあるだけで空間の印象は大きく変わります。 タイルのある暮らしとは、「自分らしく、心地よく空間を整える」ことに価値を見出すライフスタイルと言えるかもしれません。

空間に“余白”をもたらす素材
タイルは、壁を支えるわけでも、断熱を担うわけでもありません。 それでも、多くの建築家や施主がタイルを選ぶのは、空間に“余白”や“個性”をもたらす力があるからです。
光の反射、手触り、陰影の出方…。 タイルは、空間の“質感”を豊かにする素材であり、住まいに奥行きを生み出します。 「必要だから」ではなく、「こうしたいから」選ばれる素材、それがタイルなのです。

経済と暮らしに見る建材選びの傾向
現代の日本では、物価の上昇とともに、支出を抑える動きが強まっています。 住宅や店舗づくりにおいても、「コスト効率」や「施工性」が優先されがちで、感性に訴える建材が後回しになる傾向があります。
その背景には、実質賃金の低下、資材費の高騰、労働力不足といった課題があり、建築現場では限られた条件のなかで最適解を求める日々が続いています。
その背景には、実質賃金の低下、資材費の高騰、労働力不足といった課題があり、建築現場では限られた条件のなかで最適解を求める日々が続いています。
また、国内の通貨供給量、いわゆるマネーストック(M2)が十分に増えていないことも大きな要因です。お金が社会全体に回らなければ、企業活動や個人の消費も活発にならず、結果として可処分所得の伸び悩みに繋がります。近年の政策では増税や財政健全化が重視される一方で、家計に届く資金が潤沢に供給されているとは言えません。 その結果として、内装材や意匠建材といった“空間の印象を左右する部分”が、コスト調整の対象として削られる場面も少なくないのです。
今の経済環境と建築の現場
2020年代以降、世界的な資源価格の上昇と円安が続いたことで、日本の建材価格も上昇基調が続いています。 輸入原材料に依存する製品では価格転嫁が避けられず、全体の建築費用を押し上げる要因となっています。
こうしたなか、設計段階から「標準化」や「VE(バリューエンジニアリング)」によって、意匠的な選択肢が削られてしまうケースも珍しくありません。
しかし一方で、「だからこそ素材にこだわる」という動きも静かに広がっています。 限られた予算の中でも、「印象を決定づけるワンポイント」としてタイルを採用する設計事務所や施主も増えており、“選ばれる建材”としてのタイルの価値はむしろ高まっているとも言えるのです。

豊かさを選ぶということ
タイルのある暮らしは、豊かさの象徴です。 それは物質的な贅沢ではなく、「選択の自由があること」「自分の感性で空間をつくること」が可能な状態を指します。
洗面所に、キッチンに、玄関に、ほんの少しだけタイルを使ってみる。 それだけで毎日の風景が少し変わり、気持ちにも変化が訪れるかもしれません。 その小さな変化が、“自分らしい暮らし”をつくっていく第一歩になります。
文化と物語を持つタイル
タイルは世界中のさまざまな文化に根差した素材です。 日本では美濃焼や常滑焼など、地域ごとに表情の異なるタイルが生まれてきました。 それらには、土、釉薬、焼き方など、長い歴史と人の手仕事が積み重なっています。
どこで作られ、どんな技術で生まれたか——。 その背景を知ることで、タイルという素材は単なる建材ではなく、文化と物語を宿す存在として空間に深みを与えてくれるのです。
また、サステナブルな視点からも、地域資源や伝統技術を活かしたタイルは再評価されつつあります。 安価で均質な工業製品とは異なる、“唯一無二”の風合いを求めて、ローカルなものづくりに注目する声も高まっています。
タイルの再評価とサステナビリティ
世界的に「大量生産・大量消費」の時代が見直されるなかで、タイルのような耐久性のある素材が再び注目されています。
施工後のメンテナンス性、長寿命、修繕の容易さなど、サステナブル建材としての利点は多く、リノベーション市場においてもその活躍の場が広がっています。

加えて、近年ではBIMやインテリアVRなどデジタル設計との親和性も高まり、設計段階からタイルの色や質感を「体験」できる環境が整ってきました。 これは、タイルの持つ「質感」や「表情」をより深く伝えるうえでも有効であり、設計者と施主のイメージ共有をスムーズにする役割を担っています。
私たちが考える「これからの暮らし」
これからの暮らしは、単に機能や価格だけで語られるものではありません。 環境、地域、文化、自分らしさ……そういった要素をどう空間に取り入れていくかが問われる時代です。
タイルは、その問いに対してとても柔軟に応えることのできる素材です。 自然素材との組み合わせ、古材との共演、カスタムカラーやパターンなど、空間の個性に寄り添いながら、静かにその場の「質」を引き上げてくれます。

タイルを通して、空間を考え、暮らしを整える。 その先には、きっと「心の余白」を大切にした豊かな時間が待っているはずです。
暮らしと空間の“記憶”を支える存在
タイルの魅力は、その場の「雰囲気」をつくるだけではありません。 長い時間をかけて空間に馴染み、住まい手と共に記憶を積み重ねていくという特性があります。
タイルは傷も汚れも経年変化も含めて「育つ素材」であり、やがて家族の記憶や日常の風景の一部になります。
たとえば、料理をしながら目に入るキッチンのタイル、朝の身支度をする洗面まわり、玄関で靴を脱ぐときに感じる床の質感。 それらすべてが、暮らしの一部として記憶に残るのです。
だからこそ、タイルは「時間」と「感情」を受け止める器のような存在だと、私たちは考えています。
まとめ
今回は「タイルのある暮らし」というテーマで、空間づくりにおけるタイルの価値や意味を、経済的背景も交えながらご紹介しました。
タイルは、空間に“余白”や“質感”を与える建材です。経済の動きとともに需要は変化しますが、選ばれる価値は失われていません 。タイルを選ぶことは、自分らしい暮らしを大切にするという意思の表れではないでしょうか。
そして、タイルには、文化や歴史、そして未来への物語が込められています。
サステナブルな時代において再び評価されているタイルの魅力は、空間の記憶に寄り添い、時間と感情を重ねる建材と言えるでしょう。
淡陶社では、さまざまな暮らしや空間に合うタイルを取り揃えています。 「タイルのある暮らし」を実現するための第一歩として、ぜひ当社の製品をご覧ください。
Webサイトからは、カタログの閲覧や無料サンプル請求も可能です。 また、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
これからも「タイル研究室」では、暮らしに寄り添うタイルの魅力を発信してまいります。